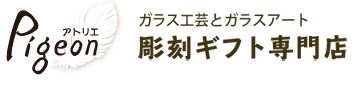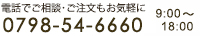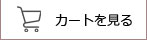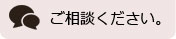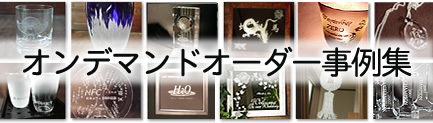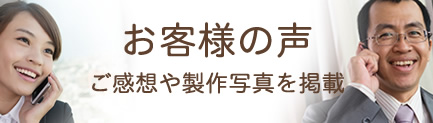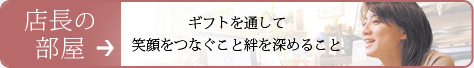| 2023年 癸卯(みずのとう) |
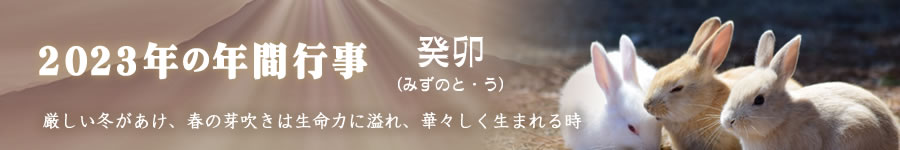
| 月 | 国民の祝日 | 行事・記念日 (下線は、豆知識へ) |
二十四節気 | 三隣亡 | ギフト準備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 元旦 9日 成人の日(第2月曜) |
2日 初荷・初商 4日 官庁御用始め/証券取引所大発会 7日 七草 10日 十日恵比須 15日 小正月 17日 冬の土用入り |
6日 小寒 (しょうかん) 20日 大寒 (だいかん) 月 |
12日(木) 24日(火) |
お年賀 〜1/7(松の内、関西は〜1/15) 成人祝 |
|
| 11日 建国記念の日 23日 天皇誕生日 |
2日 冬の土用明け 3日 節分 (恵方は南南東やや南) 14日 バレンタインデー |
4日 立春 19日 雨水 (うすい) |
10日(金) 22日(水) |
お年賀遅れたら 〜2/4(立春)までに「寒中お伺い」 バレンタインデー |
|
| 21日 春分の日 | 3日 ひな祭り 14日 ホワイトデー 16日 社日 18日 彼岸入 21日 彼岸(彼岸の中日) 24日 彼岸明け |
6日 啓蟄 (けいちつ) 21日 春分 |
9日(木) 21日(火) |
桃の節句(雛飾りは2/19の雨水ごろから3/6啓蟄までが縁起よし) ホワイトデー 退職祝い |
|
| 29日 昭和の日 |
1日 エイプリルフール 17日 春の土用入り |
5日 清明 (せいめい) 20日 穀雨 (こくう) |
2日(日) 6日(木) 18日(火) 30日(日) |
入学祝 就職祝い |
|
| 3日 憲法記念日 4日 みどりの日 5日 こどもの日 |
2日 八十八夜 5日 端午の節句 14日 母の日 |
6日 立夏 (りっか) 21日 小満 (しょうまん) |
17日(水) 29日(月) |
端午の節句 初節句祝いの 鎧兜や五月人形を送る場合は、当日より20日前には届くように(10〜20日飾るのがベスト) 母の日 |
|
| 1日 衣替え 18日 父の日 30日 大祓(夏越) |
6日 芒種 (ぼうしゅ) 21日 夏至 (げし) |
13日(火) 25日(日) |
父の日 | ||
| 17日 海の日(第3月曜日) |
7日 七夕 15日 盆/中元 20日 夏の土用入り 30日 土用の丑の日 |
7日 小暑 (しょうしょ) 23日 大暑 (たいしょ) |
11日(火) 23日(日) |
お中元 7月初旬〜中旬 7月中旬すぎたら、「暑中見舞い」として |
|
| 11日 山の日 | 7日 夏の土用明け | 8日 立秋 (りっしゅう) 23日 処暑 (しょしょ) |
4日(金) 9日(水) 21日(月) |
残暑見舞い 8/8日以降 |
|
| 18日 敬老の日(第3月曜) 23日 秋分の日 |
10日 十五夜(中秋の名月) 14日 メンズバレンタインデー 20日 彼岸の入り 22日 社日 23日 彼岸(彼岸の中日) 26日 彼岸明け |
8日 白露 (はくろ) 23日 秋分 |
2日(土) 17日(日) 29日(金) |
敬老の日 | |
| 9日 スポーツの日 (第2月曜) | 1日 衣替え 21日 秋の土用入 31日 ハロウィン |
8日 寒露 (かんろ) 24日 霜降 (そうこう) |
15日(日) 27日(金) |
||
| 3日 文化の日 23日 勤労感謝の日 |
7日 秋の土用明け 16日 ボジョレーヌーボー解禁(第三木曜) 15日 七五三 |
8日 立冬 (りっとう) 22日 小雪 (しょうせつ) |
13日(月) 25日(土) |
七五三 11月初旬〜11/15 七五三内祝 〜11月末 |
|
| 24日 クリスマスイブ 25日 クリスマス 31日 大晦日/年越し |
7日 大雪 (たいせつ) 22日 冬至 (とうじ) |
10日(日) 22日(金) |
お歳暮 関東:12月初旬〜12/31 関西:12/13〜12/31 クリスマス |
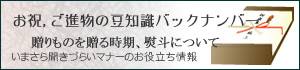
知っ得ギフト<お祝い、ご進物の豆知識バックナンバー>
六曜の意味 (六曜は時間の吉凶を知るためだった?由来など)
| 大安 | 万事に吉。結婚式には特に良い |
| 赤口 | 午前・午後は凶。正午が吉ではあるが祝い事には大凶。 仏滅が物事の消滅に対し、赤口は万事消滅を表す |
| 先勝 | 午前が吉。午後が凶。 |
| 友引 | 朝夕は吉。「友を引く」ということで葬式は行いません |
| 先負 | 午前が凶。午後が吉。 |
| 仏滅 | 万事によくないとされる日。物事の消滅を表すので別れごとにはよい |
三隣亡
| その日に建築すれば、近隣三軒まで災いが及ぶとされる日。 1・4・7・10月は亥の日、2・5・8・11月は寅の日、3・6・9・12月は午の日が 三隣亡と決められています。 大安吉日であっても、三隣亡の日は避けたほうがよいでしょう |
三伏日
| 夏至以降の三度目の庚の日を初伏、四度目の庚の日を中伏とし、立秋直後の庚の日を末伏として、三伏といいます。 庚は金の気で、夏の火勢が庚の金を剋するため、播種・旅行・婚姻などの和合事は忌むべき日とされています。 |